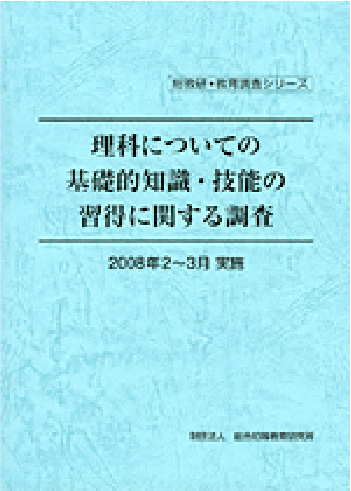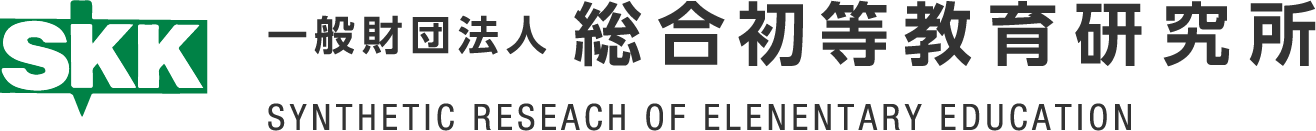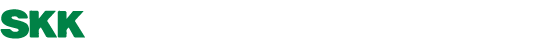理科についての基礎的知識・技能の
習得に関する調査
本調査の概要
1.調査の実施について
(1)調査の目的
「理科についての基礎的知識・技能」とは、子どもたちが生活していく上で最低限知っておきたい知識、物事を考える手だてになる知識、及び最低限身につけておきたい観察・実験技能のことである。
今回の調査は、「理科についての基礎的知識・技能」に焦点を当て、全ての子どもたちに最低限習得させたい知識・技能について、子どもたちがそれらをどの程度習得しているかを、学年別及び領域(知識A領域、知識B領域、知識C領域、技能)別に把握するところに主要な目的がある。
(2)調査の内容
調査問題は、「知識A領域」(生物とその環境)、「知識B領域」(物質とエネルギー)、「知識C領域」(地球と宇宙)、及び「技能」の4つの領域において、第3学年から第6学年理科で取り上げられる内容から、各学年の問題を作成した。各学年に関する問題は、それぞれ次のような内容を問う問題から構成した。
【調査問題3年】
| 知識A領域 | 昆虫や植物の育つ順及び部分の名称を問う問題 |
|---|---|
| 知識B領域 | 光、電気及び磁石の性質を問う問題 |
| 知識C領域 | 太陽と地面の様子(かげのでき方、温まり方)の関係について問う問題 |
| 技能 | 第3学年で取り扱う代表的な観察・実験器具(例えば、虫眼鏡、温度計、遮光板)の使い方を問う問題 |
【調査問題4年】
| 知識A領域 | 昆虫や植物の季節による様子の違いを問う問題 |
|---|---|
| 知識B領域 | 空気や水、金属のかさの変化、及び温まり方を問う問題 電気の通り道、乾電池のつなぎ方の名称を問う問題 乾電池、光電池の働きを問う問題 |
| 知識C領域 | 月や星の動き方を問う問題 水の状態変化について問う問題 水の様子を表す名称を問う問題 |
| 技能 | 第4学年で取り扱う代表的な実験器具(アルコールランプ、検琉計)の使い方を問う問題 |
【調査問題5年】
| 知識A領域 | 植物の発芽や成長、動物の発生や成長について問う問題 |
|---|---|
| 知識B領域 | 物の溶け方(物質による溶け方の違い、水の温度と量による溶け方の違いなど)について問う問題 てこ及びふりこの働きを問う問題 |
| 知識C領域 | 気の変化について問う問題 流水の働き(速さや量との関係)を問う問題 |
| 技能 | 第5学年で取り扱う代表的な観察・実験器具(例えば、顕微鏡、上皿てんびん)の使い方及び実験操作を問う問題 |
【調査問題6年】
| 知識A領域 | 生物の体のつくりと働きを問う問題 生物と環境の関わりについて問う問題 |
|---|---|
| 知識B領域 | うすい塩酸と金属の反応について問う問題 燃焼前後の空気の成分変化、及び二酸化炭素の性質を問う問題 電磁石の極や電磁石を強くする方法について問う問題 |
| 知識C領域 | 地層や大地の変化について問う問題 |
| 技能 | 6学年で取り扱う代表的な実験器具(例えば、リトマス紙、気体検知管)の使い方を問う問題 |
実施方法
(1) 実施の時期
平成20年2~3月
調査時間は各学年それぞれ約30分
(2) 実施した対象学年
第3学年~第6学年
(3) 実施校数及び児童数
実施した小学校8校、第3学年20学級638名、第4学年20学級614名、第5学年19学級621名、第6学年20学級533名、合計2,406名。
2.調査研究書の内容から
1)正答率から見た調査の結果
【表1】 問題別に見る正答率(全体)(単位:%)
| 知識A 正答率範囲 |
知識A 平均 |
知識B 正答率範囲 |
知識B 平均 |
知識C 正答率範囲 |
知識C 平均 |
技能 正答率範囲 |
技能平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3学年 | 66.0~96.9 | 85.6 | 93.9~100.0 | 97.9 | 87.8~91.7 | 89.8 | 74.6~98.6 | 89.6 |
| 第4学年 | 70.0~88.1 | 81.8 | 39.2~97.4 | 80.2 | 74.7~97.9 | 85.5 | 44.9~98.5 | 82.6 |
| 第5学年 | 47.8~97.9 | 77.7 | 65.5~92.1 | 79.0 | 74.1~97.6 | 86.3 | 63.6~96.3 | 82.8 |
| 第6学年 | 70.0~96.1 | 89.5 | 67.2~97.2 | 80.3 | 80.1~93.2 | 88.7 | 81.1~98.7 | 90 |
その学年で最も平均正答率が低かった領域
その学年で最も平均正答率が高かった領域
【表2】 学年の知識・技能別の見る正答率(単位:%)
| 知識 | 技能 | 全体 | |
|---|---|---|---|
| 第3学年 | 91.4 | 89.6 | 90.9 |
| 第4学年 | 82.1 | 82.6 | 82.1 |
| 第5学年 | 80 | 82.8 | 80.5 |
| 第6学年 | 84.8 | 90 | 85.3 |
その学年で最も平均正答率が高かった領域
【表3】 学年・領域別に見る正答率の児童の割合(単位:%)
| 知識A領域正答率 | 知識B領域正答率 | 知識C領域正答率 | 技能正答率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80%以上の 児童の割合 |
50%未満の 児童の割合 |
80%以上の 児童の割合 |
50%未満の 児童の割合 |
80%以上の 児童の割合 |
50%未満の 児童の割合 |
80%以上の 児童の割合 |
50%未満の 児童の割合 |
|
| 第3学年 | 69.1 | 7.3 | 96.7 | 0.0 | 77.7 | 7.3 | 77.9 | 1.0 |
| 第4学年 | 55.1 | 8.8 | 53.1 | 3.4 | 68.8 | 4.3 | 81.4 | 2.5 |
| 第5学年 | 59.5 | 12.5 | 63.2 | 9.6 | 73.4 | 2.9 | 64.9 | 4.2 |
| 第6学年 | 83.1 | 2.1 | 58.1 | 10.2 | 86.8 | 4.9 | 86.1 | 1.7 |
第3学年から第6学年まで学年ごとの調査結果を、表1、表2及び表3のように再構成してみると、次のような点に気づくことができる。
・全学年を通して、各領域の平均正答率は77.7~97.9%と高い。
・設問によっては正答率が著しく低いものがある。
・知識B領域の正答率は、第3学年は他の領域と比べて高いが、第5学年と第6学年は他の領域よりも低くなっている。
・第3学年は知識の方が技能よりも習得できているが、第5学年と第6学年は技能の方が知識よりも習得できている。
・全学年・領域を通して、基礎的知識・技能について、知っている児童と知らない児童が両極端に別れているということはない。
(2)調査の結果からわかること
・子どもたちの「理科についての基礎的知識・技能」の習得状況は、全体的に見て良好である。
・著しく正答率の低い設問は、理科の用語について問うた問題であり、特に第4学年において「回路」、第5学年において「発芽」という用語が身についていない。
・知識B領域は、第3学年においては他の領域よりも習得できているのに対し、第5学年及び第6学年では、他の領域より習得できていない。つまり、学年が上がると知識B領域が身につきにくくなっている。
・第5学年及び第6学年は知識よりも技能の習得状況が良い。
課題
【「理科についての基礎的知識・技能」の習得における課題】
・理科用語(科学用語)が身についていない。
・知識B領域は、学年が上がると他の領域より身についていない。
【調査側の課題】
・高学年は技能の習得状況が良いと判断できるが、技能において、「解ける」と「できる」は違うことがある。そのため、技能に関しては、習得状況を詳しく見るためには、パフォーマンステストの必要性も挙げられる。
(3)学校や家庭における指導のあり方
・指導する側が「科学用語は現象を峻別するためのものである」という認識を持つ。
・繰り返して学習させる。
・学習環境を整える。
・科学的な見方・考え方を段階的に身につけさせる。
・自分との関わりや実生活との関わりの中で理解させる。
今回の調査から、自分たちの身のまわりの自然環境・事象について学び、理科についてもっと知ろう、知りたいと思う子どもたちが、科学分野のよりよい発展を担っていくといえる。
調査研究書について
-
1.規格 B5判64ページ
2.発行 平成21年5月20日
3.構成
調査研究編
I なぜ、基礎的知識・技能の調査か
II 調査の概要
III 調査結果と分析・考察
IV 調査の総括
展望編
〈調査結果から見た今後の課題〉
・中学年からの積み上げを大切に
・「何を育てたいのか」という意識をもとう
〈特別論文〉
資料編
調査問題と解答
調査結果データ
※調査結果データは、本ページPDFマークの箇所でもご覧いただけます。